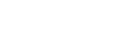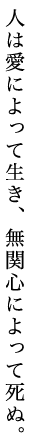
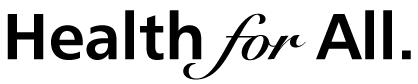
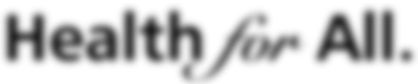
プライマリヘルスケア(Primary Health Care: 以下、PHC)とは、1970年代後半に、世界の保健・医療におけるアクセスの改善、公平性、住民参加、予防活動重視などの実現を求めて形成された理念かつ方法論である。 簡単に言い換えると、「すべての人にとって健康を基本的な人権として認め、その達成の過程において、住民の主体的な参加や自己決定権を保障する理念であり、方法・アプローチでもある」と言える。
PHCは1978年、旧ソ連邦カザフ共和国の首都アルマ・アタで出された、歴史的な宣言が基礎になっている。このアルマ・アタ宣言 によると、 「PHCとは、実践的で、科学的に有効で、社会に受容されうる手段と技術に基づいた、欠くことのできない保健活動のことである。 アルマ・アタ宣言では、’Health for All by the Year 2000’(2000年までにすべての人に健康を)が目標とされた。一義的にはPHCは途上国の開発課題として構想された面があり、 その意味では、BHN(Basic Human Needs)や「もう一つの開発」など、近代化論による開発の弊害への反省に立った第二世代の開発論と言えるが、 それ以外に、世界人権宣言(1948)や国連社会権規約(1966)に謳われた「人権としての医療」の思想を継ぐものである。 また、CBR(地域リハビリテーション)や参加型教育法(PRAなど)との交流や相互啓発を見逃すこともできない。
先進国でも、西欧諸国やカナダ、オーストラリアなどは、PHCを、地域医療を効率的に運用し、公正なアクセスを実現する意味で、重視してきた経緯がある。 日本においても、戦後長野県の佐久病院などの農村地域で試みられてきた予防重視の住民参加型保健活動は、PHCのモデルとなった。 PHCは、2000年までという目標を達成できなかったという意味で、批判を浴び、また早くも1979年には「選択的PHC」が暫定戦略(Interim Strategy)としてWalshらにより提唱され、理論的にも現場レベルでも論争や混乱を招いた。 しかし、WHOやPAHOは、21世紀の世界の保健課題を達成する上で、改めてPHCの遺産を肯定的に捕らえ、取り組む姿勢を示している。 その意味で2008年には、WHOから歴史的に重要な2つの文書が出されている。 一つはPHCの21世紀版、“World Health Report Primary Health Care: Now More Than Ever” (世界健康白書 プライマリ・ヘルス・ケア:それはこれまでにも増して必要とされている) もう一つは、 “Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health“ (世代内の健康格差を縮める:健康の社会的決定要因への働きかけを通しての健康における公正の達成) これは「健康の社会的決定要因」という近年、重視されているPHCと密接に関連する考え方だ。 この報告書の起草者の一人が、国会原発事故調査委員会の黒川清氏(委員長)である。
そして21世紀中葉に向かう現在の日本は、世界に先駆けて「少産多死」という人口転換 、いわば第4の健康転換期 に突入しており、財政も含めて大変な時代である。 だからこそ、PHCについて考え直すことが非常に重要な時期であるといえる。
(本田徹理事の説明を引用)
アルマ・アタ宣言( Declaration of Alma-Ata)は、1978年9月に、現在のカザフスタン共和国アルマティ(当時は、 ソビエト連邦アルマ・アタ) で開催された第一回プライマリヘルスケアに関する国際会議(WHO、UNICEF主催)で採択された宣言文のことである。 すべての政府、保健・開発従事者、世界の市民社会が、世界中のすべての人々の健康を守り促進するため、至急のアクションをとる必要性を強調した。 本宣言はまた、プライマリヘルスケア(PHC)の大切さを明確に示した最初の国際宣言でもある。 本宣言以降、PHCアプローチは、「すべての人々に健康を」(Health For All:HFA)イニシアティブの目標達成の鍵として世界保健機関加盟国に受け入れられてきた。
人口転換とは、経済・社会の持続的な発展にともなって、人口が多産多死から多産少死を経て、やがて少産少死にいたる過程を意味する。 現在の先進諸国はこの人口転換によって、人口はほぼ一定かやや減少にて転じ、老年人口の割合が高くなってきている。 また、発展途上地域では、多産少死の状態がいわゆる人口爆発の原因となっている。 同様に、疾病構造は、周産期疾患や結核など感染症が主体の段階から、肥満、高血圧、糖尿病、がんなど非感染症が主要な段階へと転換する。 このような疾病構造の変化を人口転換にならって疫学転換(epidemiologic transition)と呼ぶ。 しかし多くの発展途上地域では、この転換がモザイク状で、感染症と非感染症両方からの負担に対応する必要に迫られている。
健康転換とは、この人口構造の転換を基にして、時代とともに人口・疾病構造の変化、保健医療制度の変化、 社会経済構造の変化が相互に影響しあいながらある国の健康問題が段階的、構造的に転換することを示すシステム概念である。
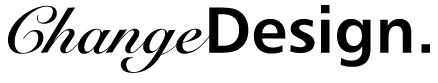
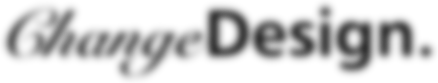
心も身体も「健康」でありたい・・・。
これは、年齢、場所、貧富、社会的境遇等によって変るものではなく、全てに等しいほど多くの人が望むものでしょう。
では「健康」っていったい何なのでしょう。
病気ではないこと? 元気なこと?・・・、これでは言いえていない感じです。
世界保健機構(WHO)では、このように定義しています。
「健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいう」(日本WHO協会訳)
納得できますが、この定義でいう「健康」になるのは、とても高いハードルのようにも思えます。
崩すのは簡単で、ともすれば普段から崩れているもののようであり、作りあげるにしてもどこか一部はうまく作れないもののように感じます。
それほど得がたいからこそ、皆が欲するものなのでしょう。
この「健康」を、自分たちで、日常や生活の中、そして身近な環境で、作り、守ることが「プライマリヘルスケア」です。
「プライマリヘルスケア」は、当初は途上国の保健・衛生・生活環境の改善のためという側面を強く持って使われてきました。
「途上国も先進国もなく、世の中の全ての人に健康を」という理念がこめられていました。
「全ての人に健康を」について、身近なところで考えてみれば、自分自身や家族、親戚、友達、同僚、ご近所さんの「健康」はどうなのでしょう。
満たされないだけでなく、困ったり、悩んだり、苦しんでいる人もいるかも知れません。
プライマリヘルスケア研究所は、そんな身近なところから、「健康」を主体的に作り守るための活動や研究をしていくところです。
この度、プライマリヘルスケア研究所はNPO法人格を取得しました。
これまで所長及び代表でありました伊藤憲祐には顧問職として引き続き会を支えていただき、僭越ながら吐師秀典が代表となりました。
文頭にあたり、諸兄諸姉の皆様には今後も変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い致します。
さて、国内外問わず、医療・保健・福祉の発展には、日進月歩の勢いが感じられます。
先進国の高度先進医療は次々と不治の病を克服し、途上国の経済成長は自国内の医療・保健の水準を向上させていますが、
一方では途上国でも先進国でも医療格差の問題がますます深刻になり、公正な解決が急がれています。
また、先進国を中心とした世界的な高齢化は福祉の多様性を進め、その多様性は障害福祉へも波及しています。
本研究所は、そうした「ヘルス」をめぐるさまざまな今日的課題に、プライマリ・ヘルス・ケアという観点から研究と活動を展開していくことをミッションとして、
あやめ診療所長の医師・伊藤憲祐によって、2008年に設立されました。
プライマリ・ヘルス・ケアを直訳すると「もっとも身近な健康問題への取り組み」と言い換えられます。
医療・保健・福祉の技術や制度が如何に発展したとしても、それらが現実的にその人にどのように届くのかがとても大切です。それは、この日本においても然りです。
人が社会から孤立していたり、病を持ちながら自らあきらめて援助を避けていたり、どうしていいか分からず誰にも相談できなかったりと、
もしかしたら本人が望んでいながらも適切なケアにアクセスできていない現状はあちらこちらにあります。
医療・保健・福祉に関わる人たちはもとより、地域の中で、本人、家族、友人、知人といった当事者になる人たちが、
望ましい(むべき)健康への一歩を踏み出すために必要なことを見つけていく研究や活動を行っていきたいと思います。
興味・関心のある方は、いつでもご連絡下さい。
平成24年9月吉日
代表理事 吐師 秀典
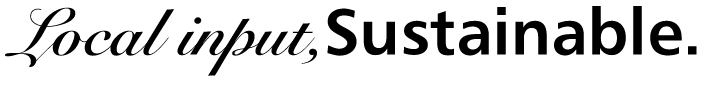
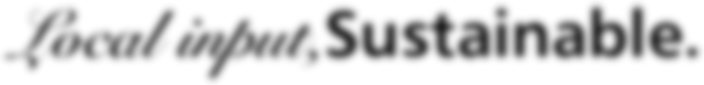
当研究所では、主に在宅ケアに従事する人々とともに、「我が国におけるプライマリヘルスケアのあり方」についての検討やそれに関連する研究活動を行なっています。
現在は、主に当法人の活動地域(台東区、墨田区)周辺で在宅ケアを行う医療従事者、訪問看護師などの地域保健従事者、 ケアマネージャー・訪問看護師などの在宅介護従事者、地域で在宅ケア活動を行うNPO(特定非営利活動法人)、行政関係者とともに、 「在宅ケアのあり方」、「在宅ケアを行う上での課題」、「人々に必要とされるケア」などについて検討を行なっています。
そのために、主に在宅ケアに従事する人々を対象に定期的に談話会を開催し、在宅ケアの現状や課題などについてのディスカッションを行い、 特に検討を深めるべき課題については、医療・保険従事者、在宅介護従事者、NPO、行政関係者など他職種により構成される研究チームによって研究活動を行なっています。
今後も、在宅ケア従事者や地域住民の方々などケアを必要とする人々・ケアを行う人々が垣根なく議論を深め、 「望ましいケアとは何か」、「望ましいケアをいかに行なってゆくか」を問い続け、「わたしたちのケア」を作り上げてゆく場でありたいと思います。
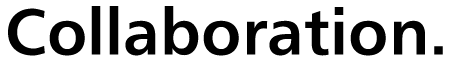
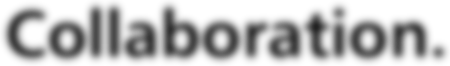
私達の理念は、プライマリヘルスケア研究所だけでなく、多くのNPO/NGOや機関からの支持と共感を得ています。
また、当研究所の附属診療所であった「あやめ診療所」は、当研究所のNPO化に伴い発展的独立を致しました。
今後も診療所の活動を通して取り組みを広げていきます。
医療法人社団哺育会 浅草病院
あやめ診療所(竜泉)
あやめ診療所(北本)
訪問看護ステーション みけ
認定NPO シェア=国際保健協力市民の会
NPO 訪問看護ステーションコスモス
NPO きぼうのいえ
NPO 友愛会
認定NPO 山友会